広電宮島線 修大協創中高前駅から徒歩1分の内科・産婦人科クリニック。
電話でのお問い合わせはTEL.082-277-1223
〒733-0842 広島市西区井口4-2-31
質問FAQ
FAQ よくある質問
| 産科Q&A | 婦人科Q&A | 内科Q&A |
産科Q&A
| 分娩予定日 | 葉酸 | 切迫流産 | 流産手術 |
| 腹帯 | インフルエンザ | 防腐剤含有ワクチン | 抗インフルエンザ剤 |
| 旅行 | 温泉 | 飲酒 | カフェイン |
| 便秘 | こむらがえり | アトピー | 食事 |
| サイトメガロウイルス | 妊娠高血圧症候群 | 蛋白尿 | 風しん |
| 子宮底長 | ワクチン接種 | 放射線検査 | スポーツ |
| つわり | 糖代謝異常 | 医薬品 | 貧血 |
| 風邪 | 羊水過多 | 羊水過少 | トキソプラズマ症 |
| 新型コロナウイルスワクチン | 異所性妊娠 | RSワクチン |
Q1.分娩予定日について教えてください。
A.
排卵日から266日後を分娩予定日としていますが、通常は最終月経開始日を基準にして計算します。
現在ではコンピュータにて正確に最終月経開始日から280日目を計算していますが、 簡便な方法として最終月経の開始日の月数に9を加え、日数に7を加えればおよその予定日が分かります。
例)最終月経開始日3月20日の場合 3月の3+9=12 20日の20+7=27 すなわち12月27日が分娩予定日となります。
例)最終月経開始日が10月25日の場合 10月の10+9=19 25日の25+7=32 19月32日となりますが、月は12月まで日は30日までで繰り越し分を調整します。19月は19−12=7月、32日は32−30=2日で月が繰り上がりますので、8月2日となります。
基礎体温にて排卵日が明らかな場合や超音波計測値で分娩予定日の補正が必要な場合もありますので、 必ず妊娠初期に病医院を受診し正確な分娩予定日を決める必要があります。
当院では、超音波計測値にて分娩予定日を最終的に決定後に妊娠カレンダーを差し上げています。
これを見れば、現在の妊娠週数がすぐに確認できます。
A.
産婦人科診療ガイドライン産科編2020では、以下のように説明することになっています。
1)妊娠前から市販のサプリメントにより1日0.4mgの葉酸を妊娠前から摂取することで、児の神経管閉鎖障害発症リスクの低減が期待できると説明する.(B)
2)特に神経管閉鎖障害児の妊娠既往がある女性に対しては、医師の管理下に妊娠前から妊娠11週末まで、1日4~5mの葉酸を服用することで、同胞における発症リスクの低減が期待できると説明する.(B)
3)神経管閉鎖障害の発症は多因子によるものであり、葉酸摂取不足のみが発症要因ではないと説明する.(B)
推奨レベル(B):勧められる.
神経管閉鎖障害は先天性の脳や脊柱に発生する癒合不全のことで、無脳症、脳瘤、二分脊椎等の病気があります。
神経管の閉鎖は妊娠6週末で完成するため、妊娠に気づいてからの摂取では遅すぎます。
妊娠1か月以上前からの摂取が必要です。
葉酸は熱に弱く調理により失いやすいため、食事からの摂取では不十分です。
それを補うためサプリメントをお勧めしていますが、ビタミンAを含んでいるものもあります。ビタミンAを妊娠初期に大量摂取すると先天異常の発症が報告されており、 許容上限摂取量は5000IUとされていますので、ビタミンAの過剰摂取には注意を要します。
葉酸パンフレット(日本医療研究開発機構 成育疾患克服等総合研究事業) Q3.切迫流産と診断されました。流産するのではないかと心配です。
A.
切迫流産の症状として、少量の性器出血、軽度の下腹部痛、恥骨上部の疼痛、腰痛、下腹部緊満感などがあります。
全妊婦の約20〜25%にこれらの症状が出現しますが、 最終的に流産に至る頻度はその半数の10%程度となります。
また枯死卵や稽留流産などの無症状のまま流産に至る例もあり、これを含めると全妊娠の約15%が流産することが知られています。
流産の原因は多岐にわたりますが、その内の過半数は胎児染色体異常などの胎児側の要因です。
胎児因子による流産は自然淘汰による不可避の流産と考えられ、治療法はありません。
即ち、流産を確実に回避する治療法はなく、安静や薬剤による治療を積極的に行わず経過観察することが切迫流産の基本的な対処法と考えます。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020においても、
「流産予防効果が確立された薬物療法は存在しない.」(推奨レベルB:勧められる)
「休職や安静による流産予防効果は確立されていないが、勤務内容等によるリスクも考慮し、個々の症例における勤務緩和や安静の必要性を判断する.」(推奨レベルC:考慮される)と記載されています。
当院ではこのような理由から、妊娠初期に出血や下腹部痛があっても安静の指示や薬物による治療は行っていません。
Q4.流産のため手術が必要と言われました。できれば受けたくありません。
A.
結論から言うと、流産手術は必ずしも必要ではありません。
流産後の妊娠成分の子宮内遺残に伴う子宮内感染を回避する目的で、妊娠継続が不可能な流産の診断が確定すれば速やかに流産手術(子宮内容除去術)を行うのが従来の一般的な対処法でした。
しかしながら流産手術に伴う子宮穿孔による内臓損傷などの重篤な副作用も稀にあるため、近年では手術的操作を避けて自然排出を期待する待機管理について多くの報告がなされています。
これらの報告を総括した結果、初期の不全流産や自覚症状を伴わない枯死卵や稽留流産においては、待機管理も治療の選択肢のひとつと考えられ、かならずしも流産手術を受ける必要はないと考えます。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020においても流産診断後の取り扱いとして、
「待機的管理、あるいは外科的治療(子宮内容除去術)を行う.」(推奨レベルA:強く勧められる)と記載されています。
なお、待機管理の場合は自然に流産が進行しますので、出血の増量や塊の排出、下腹部痛は必ずありますし、これらの症状がいつ発現するかの予測は不可能です。
当院では、仕事をされている方などで急激な下腹部痛や多量の出血が起きては困る場合には、流産手術を行うようにしています。
手術に対する不安感の強い方や気管支喘息などで麻酔合併症が予測されるような場合は、自然流産を待つことも可能です。
当院では、患者様の仕事や家庭の事情にあわせて治療法を選択しています。
流産進行時に救急車を要請する方がいらっしゃいますが、流産により命を落とすことはありません。決して救急車を要請しないでください。
これについては、2021年9月15日のブログで触れています。
Q5.腹帯を巻く必要がありますか?
A.
結論から言うと、腹帯をする理由はないと考えています。
当院では腹帯を着用する指導はしていませんので、妊娠5か月の戌の日に腹帯を着帯する行事もしていません。
しかしながら昔からのしきたりや風習も大事ですので、 妊娠5か月の戌の日にそれまで無事に育ったことの喜びとその後の無事な分娩を祈念してご家族でお祝いすることは意義のあることだと思います。
そもそも人間も動物ですので、腹帯の力を借りなくても妊娠維持や分娩ができる体になっています。
事実、日本以外の国では腹帯をしなくても、ちゃんと分娩しています。
妊娠5か月の戌(イヌ)の日に腹帯を捲く習慣は、日本独自のものです。
犬は軽いお産でたくさんの赤ちゃんを産むことより、安産を祈念して妊娠5か月の戌の日に腹帯を捲く習慣が出たようです。
あくまでも習慣で、医学的・科学的には腹帯により安産になる根拠はないと考えています。
1.胎児が大きくなりすぎないように、きつく腹帯を巻く必要があるか?
答えは必要ありません。
腹帯をきつく巻くと、大静脈といって背骨の横を通っている大きな静脈を圧迫することになります。
その結果、循環が悪くなり足の浮腫や静脈瘤(静脈が大きく膨らんで浮き出る状態)が出現します。
また大動脈も圧迫される結果、腎臓への血液の流れが減少します。
腎臓への血流を確保するために血圧を上げる必要が出てきますので、腎臓からアンギオテンシンという血圧を上げるホルモンが分泌されます。
その結果、母体は高血圧となり危険な状態となります。
腹帯をきつく巻くと胎児が大きくならないのは事実のようですが、これは胎盤への血流が悪くなり胎盤機能不全による発育障害の結果だと考えています。
腹帯をきつく巻くことは、むしろ母体にも胎児にも危険な状態と考えられます。
2.分娩後にお腹がゆるんで元に戻らなくなるので腹帯をきつく巻く必要があるか?
この答も必要ありません。
分娩時には、胎児を娩出するために骨盤の底の筋肉が弛んでいます。
そのような状態で腹帯をきつく巻くと、お腹の中の圧力が骨盤の底の方に集中しますので、骨盤底筋肉の回復が悪くなります。
その結果、尿失禁、痔、子宮脱などの原因となります。
いずれにしても、人間も動物である以上は自然に分娩やその後の妊娠に向けての回復ができる体になっていますので、腹帯の力を借りずに自然体で臨まれたらよいと思います。
Q6.妊娠中にインフルエンザワクチンの接種は可能ですか?
A.
産婦人科診療ガイドラインー産科編2020では、「妊婦へのインフルエンザワクチン接種はインフルエンザの予防に有効であり、母体および胎児への危険性は妊娠全期間を通じてきわめて低いと説明する.」(推奨グレードB:勧められる)と記載されています。
すなわち、妊娠初期を含め妊娠週数を問わずワクチン接種は可能です。
妊婦がインフルエンザに罹患すると肺炎などの重篤な合併症を起こしやすいので、当院では積極的に妊娠中のワクチン接種を勧めています。
ワクチン接種後の効果が発現するまでに2〜3週間かかりますので、10月〜11月の時期での接種をお勧めしています。
Q7.防腐剤を含有したインフルエンザワクチンを接種しても大丈夫ですか?
A.
日本のインフルエンザワクチンにはチメロサール含有製剤と非含有製剤があります。
チメロサールは有機水銀であるため、妊婦はチメロサール非含有製剤を選択する傾向がありました。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020の解説には、「チメロサールを含んでいる製剤もその濃度は 0.004~0.008mg/mlと極少量であり、胎児への影響はないとされている。懸念されていた自閉症との関連も否定された。したがって、チメロサール含有ワクチンを妊婦に投与しても差し支えない.」と記載されています。
当院では、チメロサール含有ワクチンも躊躇せずに接種することをお勧めしています。
妊婦のインフルエンザワクチン接種の見解はQ6.をご覧ください。
Q8.妊娠中や授乳中でも抗インフルエンザ剤は服用可能ですか?
A.
米国疾病予防局ガイドライン(2007年)では、抗インフルエンザ薬を投与された妊婦および出生した児に有害事象の報告はないと記載されています。
妊婦インフルエンザの重症化を予防する服薬の利益を考えれば、妊娠中に服用する利益の方が薬剤副作用の不利益より大きいと考えます。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020においても、
1)インフルエンザに感染した妊婦・分娩後2週間以内の褥婦への抗インフルエンザウイルス薬剤投与は重症化を予防するエビデンスがあると説明する.(推奨グレードB:勧められる)
2)インフルエンザ患者と濃厚接触した妊婦・分娩後2週間以内の褥婦への抗インフルエンザウイルス薬投与は有益性があると説明する。(推奨グレードB:勧められる)
と記載されており、積極的な抗インフルエンザウイルス剤による加療が望まれます。
米国疾病予防局では、抗インフルエンザ剤を服用しながらの授乳は可能としています。
また、母乳自体に新生児への感染の可能性はないとされています。
新生児への感染の危険性を少なくするために、頻回に手洗いしたりマスクを当てる必要はあります。
Q9.妊娠中の旅行は可能ですか?
A.
お腹の痛みや出血などの流産や早産の兆候がなければ、妊娠中の旅行は可能と考えます。
妊娠週数としては、妊娠12週から28週ぐらいまでが最も旅行に適していると考えます。
まず、「妊娠中は、血液が固まりやすい状態になっている。」ということに気をつけてください。
このため深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)の予防対策が重要です。
長時間座席に座っている場合は、座ったままで足の上げ下げをするなど運動をする、適度な水分を摂取する、服装をゆったりしたものにするなどの注意が必要です。
また、航空機や鉄道を利用する場合は、立席しやすいように座席を通路側に確保して時々歩行するなどの工夫が必要です。
ツアー旅行を利用する場合には、観光スポットを短時間で転々とする観光主体のものよりも、ゆったりと時間を楽しむ滞在型のものを選ぶとよいでしょう。
車社会の現在では、旅行に限らず普段の生活においても妊婦が車に乗車する機会が増えています。
旅行の場合は、1時間乗車したら10分休むことを目安にしたらよいと思います。高速道路を利用する場合は、サービスエリアを利用しながら下車して体を動かすことを考えたらよいと思います。
妊婦とシートベルト装着の問題は重要です。シートベルトの正しい装着により交通事故時の母体/胎児の障害軽減が期待できます。着法としては、斜めベルトは両乳房の間を通し、腰ベルトは恥骨上に置き、いずれのベルトも妊娠子宮を横断しないことが重要です。
航空機を利用しての旅行では、妊娠週数により診断書、同意書の提出や医師の同伴を求められる場合があります。妊娠10ヶ月に入ってからは、診断書、同意書、医師の同伴などが必要なことがありますので、利用する航空会社への確認が必要です。国際線では、妊娠9ヶ月以降の搭乗を認めない航空会社もあります。
客室内の気圧は調整されていますが、巡航高度では標高2,000から2,500mの気圧と同等となっています。すなわち、富士山の5合目あたりの気圧となっています。また、空気中酸素濃度は地上の約75%となっています。胎盤機能不全などで低酸素症が胎児に影響を及ぼすと考えられる場合などは、搭乗を避けるべきです。
鉄道を利用しての旅行は、振動も少なく比較的安全と考えますが、重い手荷物を持っての乗換などは控える方がよいでしょう。
Q10.妊娠中に温泉に入れますか?
A.
温泉施設内の掲示板には、温泉の禁忌症として「妊娠中(特に初期と末期)」と掲示されています。
日本療養泉規定に基づく掲示ですが、環境庁自然保護局長通知の温泉の泉質別禁忌症にはどの泉質にも妊婦が禁忌の記載はありません。
温泉の成分が胎児や母体に悪影響を及ぼすとは考えられません。
家庭でもお風呂に入りますので、温泉に入ってはいけない理由はありません。
一般的な注意点として、長湯を避けて10分以内の入浴にする、感染を避けるため衛生管理の行きとどいた温泉を利用するなどの注意は必要です。
Q11.アルコールを飲んでいたので胎児への影響が心配です。
A.
妊娠以前よりお酒を飲んでいたとしても、アルコール依存症や多量の連日摂取でなければ胎児への大きな影響は無いと考えます。
アルコールは胎盤を通過します。
胎児はアルコールを処理する能力が殆どないため、影響を強く受けます。
胎児性アルコール症候群として、胎児期より始まる発育障害と頭蓋、顔貌、手足、心臓血管の異常が認められます。
1日1杯程度の飲酒であれば影響はないという報告もありますが、医学的に飲酒量に対するエビデンスはありませんので、妊娠が分かった時点でお酒は控えた方がよいと考えます。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020では、以下のように記載されています。
飲酒習慣のある妊婦は以下のことを念頭において管理する.(推奨グレードB:勧められる)
1)妊娠中の飲酒は母児へのリスクがあること
2)禁酒により母児へのリスクが回避できる可能性があること
Q12.妊娠中にコーヒーや紅茶を飲んでも大丈夫ですか?
A.
カフェインを含むコーヒーや紅茶等を飲むことは、少量であれば妊娠中でも大丈夫です。
妊娠以前からコーヒー、紅茶を飲んで楽しんでいる方は多いと思いますし、気持ちを落ち着かせたりストレスを和らげる効果も期待できます。
しかしなから、カフェインは胎盤を通過して胎児に移行することも分かっています。
多量のカフェイン摂取で流産率が上昇したり、死産や新生児死亡の原因となる報告もあります。
多量の摂取は控えて、1日に1〜2杯程度の摂取にした方がよいと考えます。
Q13.便秘がひどいのですが、下剤は使えますか?
A.
妊娠初期はつわりで水分や繊維分が摂取にくいことや、妊娠を維持するために分泌される黄体ホルモンの作用で腸管の動きが悪くなり便秘になりやすくなります。
また、妊娠中期は増大した子宮が腸管を圧迫して腸の動きが悪くなり便秘になります。
妊娠中の便秘は、腸管の動きが悪くなり腸の内容物の停滞することにより水分が吸収されて便が硬くなる事による弛緩性便秘が殆どです。
先ずは規則正しい生活を送り、特に朝食を摂取して朝食後にトイレに行く習慣をつける事が重要です。
また、食生活で十分な水分や繊維分を摂ることも重要です。
野菜類、果物、海藻、コンニャクなどに食物繊維が多く含まれています。
生活習慣の改善でも便秘が続く場合には薬物治療を行います。
薬物としては、酸化マグネシウムが妊娠中に最もよく使われます。
マグネシウムイオンは腸壁から吸収されないため、体液と腸管内の水分が等張となるように水分が腸管内に保たれ腸の動きがよくなります。
また、習慣性がないために長期間連用することも可能です。
それでも無効な場合は、ラキソベロン液を併用することがあります。
薬剤によっては子宮収縮を誘発することもありますので、産婦人科医とよく相談して服用することが重要です。
Q14.ふくらはぎの痙攣をよく起こします。
A.
ふくらはぎの痙攣、いわゆる「こむら返り」が妊娠中はよく起こります。
原因としてカルシウムの不足やリンの過剰が考えれれていますが、増大した子宮の神経の圧迫や過剰な運動などが原因のこともあり、種々の要因が絡んでいます。
妊娠中期から後期の夜間就寝中によく発生します。
治療は運動中のこむら返りと同様で、足を伸ばしてつま先を頭の方向に引き上げてアキレス腱を伸ばすようにすると早く筋肉の痙攣が治まります。
また、痙攣を起こした筋肉部分をマッサージをしたり温めたりすることも有効です。
カルシウムの摂取は必要ですが、牛乳にはリンが含まれますので過剰な牛乳の摂取は好ましくありません。
就寝前にアキレス腱を伸ばす運動をしたり、長い靴下を着用してふくらはぎを温めることも有効です。
リンを含まないカルシウム剤の服用や、芍薬甘草湯などの漢方薬が有効なこともあります。
まれに静脈血栓症などが潜んでいる場合もありますので、ふくらはぎの強い痛みなどの場合は注意を要します。
Q15.妊娠中の食事制限で生まれてくる子のアトピーが予防できますか?
A.
最近、生まれてくる子供のアトピー予防対策として、妊娠中に牛乳や卵を摂取しない妊婦さんが見受けられます。
多くの研究から、妊婦自身や既に生まれている子供に植物アレルギーの指摘が無ければ、アトピーを予防する目的で妊娠中や授乳期に食事制限をすることは意味がないと考えられています。
妊娠中の母体の食事制限で生まれてくる子供のアトピーが予防できるエビデンスはありません。
根拠のない情報に基づく極度な食事制限をする事により、母体の栄養バランスを崩すことになり、胎児の発育不良につながる危険性も出てきます。
Q16.妊娠と食事について
A.
妊娠中に注意が必要な食中毒菌としてリステリア感染があります。
妊娠中は一般の人よりもリステリア菌に感染しやすくなり、赤ちゃんに影響がでることがあります。
リステリア菌は、食品を介して感染する食中毒菌で、塩分にも強く、冷蔵庫でも増殖します。
ナチュラルチーズ(加熱殺菌していないもの)、肉や魚のパテ、生ハム、スモークサーモンなどがリステリア食中毒の主な原因食品となりますので、避けたほうがよいでしょう。
また、冷蔵庫を過信せず十分に加熱処理することが重要です。
魚は良質なたんぱく質や、血管障害の予防やアレルギー反応を抑制する作用があるDHA、EPAを多く含み、またカルシウムなどの摂取源でもあり、妊婦の栄養バランスのよい食事をとるためには欠かせない食材です。
ところが、魚には食物連鎖によって自然界に存在する水銀が取り込まれています。
魚の摂取により水銀が取り込まれ、胎児に影響を及ぼす可能性がありますので、魚の種類と量に気を付ける必要があります。
具体的な種類と量に関しては、下記の厚生労働省魚に関する情報をご参照ください。
魚について(厚生労働省)
Q17.サイトメガロウイルス感染症について
A.
先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症のテレビ報道があったこともあり、妊娠中の検査についての質問をよく受けるようになりました。
妊婦のCMV感染スクリーニング検査の有用性は、児障害程度の予測が困難、有効な胎児治療がない、ワクチンがない、感染児の殆どが症状が出ず治療法が決まっていないなどの理由で、結論が出ていないとされています。
妊婦のCMV抗体スクリーニング検査の有用性は確立されていないとされており、当院では妊婦スクリーニング検査にCMV抗体検査は取り入れていません。
超音波検査で胎児発育不全、脳室拡大、小頭症、脳室周囲の高輝度エコー、腹水、肝脾腫などを認めた場合には、胎児感染を疑います。
CMVIgG抗体検査をして陰性の場合は妊娠中に感染を起こす可能性がありますので、感染予防の対象となります。
ほとんどが乳幼児からの水平感染のため、手洗いの励行や乳幼児との接触を避けることで感染が予防できる可能性があります。
母子感染の実態把握及び検査・治療に関する研究班のサイトメガロウイルス妊娠管理マニュアルでは、感染予防対策として以下が挙げられています。
●以下の行為の後には、頻回に石けんと水で15〜20秒間は手洗いをしましょう.
おむつ交換
子どもへの給仕 子どものハナやヨダレを拭く
子どものおもちゃを触る
●子どもと食べ物、飲み物、食器を共有しない.
●おしゃぶりを口にしない.
●歯ブラシを共有しない.
●子どもとキスをするときは、唾液接触を避ける.
●玩具、カウンターや唾液・尿と触れそうな場所を清潔に保つ.
Q18.妊娠高血圧症候群について
A.
妊娠高血圧腎症は、現在では英語の略号でHDP(Hypertensive disorder of pregnancy)と表記されます。
妊娠時に高血圧を認めた場合、妊娠高血圧症候群とされます。
妊娠高血圧は、妊娠20週以降に初めて高血圧が発症し分娩後2週までに正常な血圧に戻る場合で、かつ妊娠高血圧腎症の定義に当てはまらないものです。
血圧の目安は、収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧が90mmHg以上の場合を高血圧と診断します。
Q19.尿蛋白陽性を認めたら?
A.
妊婦健診での蛋白尿スクリーニングは試験紙法による尿蛋白半定量で行います。
2回以上連続して≧1+を認めた場合と1回でも≧2+を認めた場合を蛋白尿スクリーニング陽性と判断します。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020では、
「蛋白尿スクリーニング陽性の場合、24時間尿中蛋白量≧300mgあるいは随時尿中での蛋白/クレアチニン(P/C)比≧0.3で蛋白尿と診断する.」(推奨グレードC:考慮される)と記載されています。
妊娠高血圧腎症は、妊娠20週以降に初めて高血圧を発症しかつ蛋白尿を伴うもので、分娩12週までに正常に復するばあいを言います。
妊娠高血圧腎症は胎盤機能不全、胎児機能不全、FGR/IUFD、早産、常位胎盤早期剥離、HELLP症候群、急性妊娠脂肪肝、子癇、DIC、急性腎不全など母児生命を危うくする重篤な合併症を併発しやすいため、診断がつくと入院管理が原則として必要です。
Q20.風疹について
A.
妊娠初期に風しんにかかると、難聴、心疾患、白内障、あるいは精神や身体の発達の遅れなどの障害をもった赤ちゃんがうまれる可能性があります。
これらの障害を先天性風しん症候群といいます。
先天性風しん症候群をなくすためには、風しんそのものをなくすしか手がありません。
しかしながら、風しんの抗体を持ってない成人がまだいますので、風しんの流行が各地で散発的に起こっているのが現実です。
従って先天性風しん症候群を予防するためには、妊婦さんが抗体を持っていることが重要です。
妊娠中はワクチン接種ができませんので、妊娠する前に抗体検査を受け、必要があればワクチン接種を受けるようにしましょう。
また、風しん抗体価(HI法)が8倍、16倍の妊婦さんは、低抗体価のため先天性風しん症候群をきたす可能性があります。妊娠中に風疹ワクチンを接種することはできませんが、次回の妊娠時に先天性風しん症候群を避けるために、分娩後にワクチン接種をして抗体価を上げることをお勧めします。
また、女性への感染経路の1位は夫から、2位は職場からのものです。男性からの感染が多いため、家庭内や職場での妊婦さんへの感染予防のためには、男性がワクチン接種を受けることも重要です。
広島市では妊娠を希望する女性や同居する男性に対して無料で風しん抗体検査を行っていますので、このような制度も活用しましょう。
風しん抗体検査(広島市)
Q21.子宮底長・腹囲測定について
A.
母子手帳には、子宮底長と腹囲を記載するようになっています。
これは胎児の発育状況等を確認するために昔からとられている方法ですが、現在では胎児発育の確認には超音波検査にて胎児推定体重を計測して正確に把握しています。
産婦人科診療ガイドライン産科編2017においては、「超音波検査を実施した場合、子宮底長測定は省略できる。腹囲測定はその有用性が不明なので省略可能である。」と記載されていました。
産婦人科ガイドライン産科編2020では、「妊婦健診ごとに以下を行う:体重測定、血圧測定、子宮底長測定(概ね妊娠16週以降)、尿検査(糖、蛋白半定量)、児心拍確認、浮腫評価」(推奨グレードB:勧められる)と記載されています。
今までは、子宮底長、腹囲測定は省略していましたが、子宮底長は計測した方がよいことになりましたので、今後の妊婦健診では子宮底長の計測を行います。
腹囲測定は有用性が不明なので省略可能です。
Q22.妊娠中・授乳中のワクチン接種について
A.
妊婦:授乳婦に対するワクチン接種は、産婦人科診療ガイドライン産科編2020では、
1)妊婦に対して
(1)生ワクチン接種は原則として禁忌である.
(2)不活化ワクチン接種は可能である(有益性投与).
2)授乳婦に対して
(1)生ワクチン接種も不活化ワクチン接種も可能背ある(有益性投与).
と記載されています。(推奨グレードB:勧められる)
ワクチンの種類は、以下のとおりです。
1)生ワクチン(定期接種)
BCG、麻疹・風疹混合(MR)、麻疹(はしか)、風疹、水痘
2)不活化ワクチン(定期接種)
百日咳・ジフテリア・破傷風混合(DPT)、ジフテリア・破傷風混合(DT)、ポリオ(IPV)、百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ混合(DPT−IPV)、B型肝炎、日本脳炎、インフルエンザ、肺炎球菌(13価結合型)、インフルエンザ菌b型、ヒトパピローマウイルス(HPV):2価・4価、肺炎球菌(23価多糖体)
3)生ワクチン(任意接種)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、黄熱、ロタウイルス:1価・5価
4)不活化ワクチン(任意接種)
破傷風トキソイド、成人用ジフテリアトキソイド、A型肝炎、狂犬病、髄膜炎菌:4価
Q23.妊娠中の放射線検査について
A.
妊娠に気付かずに放射線検査を受けたなどで、胎児への影響についての相談をよく受けます。
また、担当医師による根拠のない助言で、不必要な精神的苦痛を受けたり不必要な中絶に悩んでいるケースにしばしば遭遇します。
結論から言うと、いかなる放射線検査も胎児への影響はないと考えてください。
国際放射線防護委員会では、胎児奇形や発育遅延などの影響を発生する胎児の放射線被曝線量を100〜200mGyとしています。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020においては、
1)受精後10日までの被曝では奇形発生率の上昇はないと説明する.(推奨グレードB:勧められる)
2)受精後11日〜妊娠10週での胎児被曝は奇形を誘発する可能性があるが、50mGy未満では奇形発生率を上昇させないと説明する.(推奨グレードB:勧められる)
3)妊娠9〜26週では中枢神経障害を起こす可能性があるが、100mGy未満では影響しないと説明する.(推奨グレードB:勧められる)
と記載されています。
以下の表に放射線検査における胎児の被曝線量を示します。
| 検査方法 | 平均被曝線量(mGy) | 最大被曝線量(mGy) |
| 単純撮影 | ||
| 頭部 | 0.01以下 | 0.01以下 |
| 胸部 | 0.01以下 | 0.01以下 |
| 腹部 | 1.4 | 4.2 |
| 腰椎 | 1.7 | 10 |
| 骨盤部 | 1.1 | 4 |
| 排泄性尿路撮影 | 1.7 | 10 |
| 消化管造影 | ||
| 上部消化管 | 1.1 | 5.8 |
| 下部消化管 | 6.8 | 24 |
| CT検査 | ||
| 頭部 | 0.005以下 | 0.005以下 |
| 胸部 | 0.06 | 0.96 |
| 腹部 | 8.0 | 49 |
| 腰椎 | 2.4 | 8.6 |
| 骨盤部 | 25 | 79 |
A.
妊娠中の運動(スポーツ)は妊婦の健康維持・増進に役立つと考えられます。
運動(スポーツ)の中には好ましいもの・好ましくないもの・危険なものがあり、好ましい運動をするように心がけましょう。
医学的・産科的に問題のある妊婦は、運動は勧められません。
重篤な心疾患・呼吸器疾患、切迫流・早産、子宮頸管無力症、子宮頸管長短縮、前期破水、持続性性器出血、前置胎盤、低置胎盤、妊娠高血圧症候群のある方は、運動は禁忌です。
具体的なものを以下の表に示します。
| 種目 | 備考 | |
| 好ましい | ウォーキング、エアロビクス、水泳、固定自転車、ヨガ、ピラティス、ラケットスポーツ | |
| 好ましくない | ホッケー、ボクシング、バスケットボール、レスリング、サッカー | 接触や外傷の危険が高い |
| 危険 | 体操競技、乗馬、重量挙げ、スキー、スケート、ハングライダー、スキューバダイビング、激しいラケットスポーツ | 転びやすく外傷を受けやす |
A.
妊娠初期に悪心(吐き気)、嘔吐、食欲不振などの消化器症状が増悪し、全身状態が障害される状態を妊娠悪阻と言っています。
基本的には、「欲しいものを欲しい時に好きなだけ食べる」ということを勧めています。
1日に何回も嘔吐して、食事が全く食べられない、水分も飲めない状態になると脱水が進みますので点滴治療が必要となります。
ビタミンB1が不足するとウェルニッケ脳症(眼球運動障害、失調性歩行、意識障害)を起こすため、点滴内にはビタミンB1を入れるようにしています。
日常生活が送れない状態になる場合は、制吐剤、胃薬を処方することもあります。
Q26.糖代謝異常スクリーニングについて
A.
妊娠初期に血糖値が高い状態が続くと胎児形態異常が起こりやすくなります。
また、糖代謝異常合併妊娠では、十分な管理・治療のもとに血糖値を正常に維持することが必要です。
治療法としては、まず食事療法。運動療法が基本となりますが、血糖コントロールができない場合にはインシュリン療法がおこなわれます。
糖代謝異常合併妊娠では、妊娠32週以降に子宮内胎児死亡の危険性が高まる、巨大児のため肩甲難産・腕神経麻痺・骨折の危険性が高まる、児の呼吸窮迫症候群が発症しやすくなる等の問題もあります。
スクリーニングとして、妊娠初期と中期(24~28週)に随時血糖測定を行います。その結果で、血糖値が100mg/dl以上の場合は、診断検査として75g糖負荷試験(75gOGTT)を行います。
75gOGTTの結果で次の基準の1点以上を満たした場合は、妊娠糖尿病と診断します。
1)空腹時血糖値 ≧92mg/dl
2)1時間血 ≧180mg/dl
3)2時間血 ≧153mg/dl
また、以下のいずれかを満たした場合は、妊娠中の明らかな糖尿病と診断します。
1)空腹時血糖値 ≧126mg/dl
2)HbA1c値 ≧6.5%
Q27.医薬品の妊娠中投与による胎児への影響について
A.
妊娠に気づかないで医薬品を服用したため、胎児への影響について相談を受けることがよくあります。
先ず、次の月経予定日あたりまでに服用した医薬品に関しては心配ないと考えてください。
All or noneの法則と言って、胎齢17日(妊娠4週3日)までに投与された医薬品は胎児の催奇形性を及ぼさないことが分かっています。受精卵の多数の細胞に傷害が起きると胎芽死亡のため妊娠継続は無くなり、少数の細胞が傷害された場合は修復され正常発生を継続することができます。そのため、「全か無か(All or none)」の時期と称しています。
妊娠4週0日が月経が始まってから4週後(28日目)になりますので、次の月経予定日あたりまでに服用した医薬品は胎児への影響はないと考えてください。
妊娠4週以降の医薬品については、胎児への影響を考える必要があります。
1)妊娠4週以降7週末
この時期は器官形成期で、胎児の中枢神経・心臓・消化器・四肢などの重要臓器が発生・分化する時期です。従ってこの時期を絶対感受期・臨界期と称して、胎児は医薬品に対して感受性が高く、催奇形性が最も問題になる時期です。次の月経予定日から1か月後までの時期の医薬品が最も問題になると考えてください。
2)妊娠8週以降12週末
この時期での医薬品は、大奇形は起こさないが小奇形を起こし得る可能性がごくわずかにあります。
3)妊娠13週以降
この時期での医薬品は、奇形を起こす可能性はありません。しかしながら、胎児機能障害を起こす可能性がわずかにあります。
通常妊娠での流産・奇形率の発生率は、流産発生率:約15%、奇形発生率:3~5%となっています。
医薬品が原因での先天異常はその中の1%程度ですので、医薬品が原因での奇形発生率は0.03〜0.05%ときわめて低いものとなります。
国立成育医療研究センターの「妊娠と薬情報センター」などを利用して相談されることも可能です。
催奇形性・胎児毒性を示す明らかな証拠が報告されている代表的医薬品を下記に示します。
(産婦人科診療ガイドライン 産科編2020より)
1)妊娠初期
| 一般名または医薬品群名 | 代表的商品名 | 報告された催奇形性・胎児毒性 |
| エレトチナート | チガソン | レチノイド胎児症(皮下脂肪に蓄積して継続治療後は年単位で血中に残存) |
| カルバマゼピン | テグレトール、他 | 催奇形性 |
| サリドマイド | サレド | サリドマイド胎芽病(上下肢形成不全、内臓奇形、他) |
| シクロフォスファミド | エンドキサン | 催奇形性 |
| ダナゾール | ボンゾール、他 | 女児外性器の男性化 |
| チアマゾール | メルカゾール | MMI奇形症候群 |
| トリメタジオン | ミレアレ | 胎児トリメタジオン症候群 |
| パルプロ酸ナトリウム | デパケン、セレニカR、他 | 二分脊椎、胎児パルプロ酸症候群 |
| ビタミンA(大量) | チョコラA、他 | 催奇形性 |
| フェニトイン | アレビアチン、ヒダントール、他 | 胎児ヒダントイン症候群 |
| フェノバルビタール | フェノバール、他 | 口唇・口蓋裂、他 |
| ミコフェノール酸モフェチル | セルセプト | 外耳・顔面形態異常、口唇・口蓋裂、遠位四肢・心臓・食道・腎臓の形態異常、他 |
| ミソプロストール | サイトテック | メビウス症候群、四肢切断 子宮収縮、流産 |
| メトトレキサート | リウマトレックス、他 | メトトレキサート胎芽病 |
| ワルファリンカリウム(クマリン系抗凝血薬) | ワーファリン、他 | ワルファリン胎芽病、点状軟骨異栄養症、中枢神経異常 |
| 一般名または医薬品群名 | 代表的商品名 | 報告された催奇形性・胎児毒性 |
| アミノグリコシド系抗結核薬 | カナマイシン注、ストレプトマイシン注 | 非可逆的第8脳神経障害、先天性聴力障害 |
| アンギオテンシン変換酵素阻害薬(ACE-1) | カプトリル、レニベース、他 | 胎児腎障害・無尿・羊水過少、肺低形成、Potter sequence |
| アンギオテンシン2受容体拮抗薬(ARB) | ニューロタン、バルサルタン、他 | |
| テトラサイクリン系抗菌薬 | アクロマイシン、レダマイシン、ミノマイシン、他 | 歯牙の着色、エナメル質形成不全 |
| ミソプロストール | サイトテック | 子宮収縮、流早産 |
| 一般名または医薬品群名 | 代表的商品名 | 報告された催奇形性・胎児毒性 |
| 非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs) | インダシン、ボルタレン、他 | 動脈管収縮、新生児遷延性肺高血圧、羊水過少、新生児壊死性腸炎 |
A.
妊娠中に貧血の指摘を受けることがよくあります。
妊娠に起因する貧血を妊娠性貧血と言い、Hb(ヘモグロビン)値が11.0g/dl未満および、またはHt(ヘマトクリット)値が33%未満のものとされています。
妊娠後期ではHb値が11.0g/dl未満を示すことがしばしばあります。
ここで注意しなければならないことは、水血症に伴うヘモグロビンの低下です。
妊娠中は胎盤にも血液を回す必要があり循環血液量(体の中の血液全体の量)が増加します。
妊娠後半期には、妊婦の循環血液量は40〜50%増加します。
この血液が希釈された状態を水血症と言っています。
水血症になることにより胎盤への血流が活発となり、胎児の発育にも好結果を示します。
ヘモグロビン11g/dl以下のみで治療を行う施設もあるようですが、水血症を起こしている妊娠後半期では妊婦貧血の診断は慎重に行う必要があります。
妊娠中の貧血は鉄欠乏性貧血が殆どですが、先ず血清鉄の低下によりヘモグロビン、ヘマトクリットが減少します。
その後、MCV(平均赤血球容積)が低下し、最後にMCHC(平均赤血球血色素濃度)が減少します。MCV、MCHCが正常であれば水血症に伴うヘモグロビンの低下なので、鉄欠乏状態ではないと考えます。
すなわちMCVが85~100fLで正常(正球性貧血)の場合は、Hb9.0~10.9g/dlば生理的血液希釈に伴うヘモグロビンの低下で治療の必要はありません。
当院ではヘモグロビンの低下のみでは治療はしておらず、 MCVも低下して真に鉄欠乏状態と考えられる症例のみ鉄剤による治療をしています。
食生活の豊かな今日の日本では鉄剤投与が必要な妊娠性貧血は非常に稀です。
Q29.妊娠中の風邪について
A.
妊娠中の風邪症状に対して、薬の処方を希望されるケースがよくあります。
急性気道感染症(いわゆる風邪)は、ウイルスによる感染がほとんどのため抗菌剤は無効です。
当院では非妊娠時に準じた治療方針としており、原則として薬の処方はしていません。
急性気道感染症については、内科Q&AのQ5.急性気道感染症についてをご覧ください。
Q30.羊水の量が多いと言われました。
A.
子宮底長が過大であれば、羊水過多を疑います。
羊水過多は、超音波断層法による羊水ポケット、最大羊水深度、羊水インデックス等を計測して評価します。
羊水ポケット(amniotic fluid pocket:AFP)は、羊水腔に描ける円の最大径のことで、2〜8cmが正常径です。
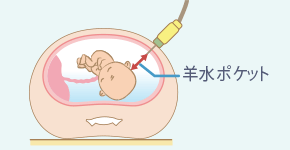
最大羊水深度(maximal vertical pocket:MVP)は、羊水腔の最大垂直深度で表します。
羊水インデックス(amniotic fluid index:AFI)は、腹部を4つの領域に分けて各領域の最大深度値の総和で5〜24cmが正常値す。
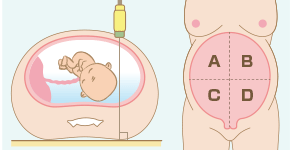
AFPまたはMVP≧8(cm)、あるいはAFI≧24(cm)を羊水過多とします。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020では、原因として以下を挙げています。
1)胎児の羊水嚥下・吸収障害:横隔膜ヘルニア、先天性嚢胞性腺腫様肺奇形、消化管閉鎖、胎便性腹膜炎、神経筋疾患、中枢神経系疾患、胎児水腫、染色体異常等
2)胎児の尿産生過剰状態(高心拍出性):双胎間輸血症候群、胎児貧血(血液型不適合妊娠、パルボウイルスB19感染、胎児母体輸血症候群、遺伝性貧血)、無心体胎児、仙尾部奇形腫、胎盤血管腫、胎児Bartter症候群等
3)妊娠糖尿病または糖尿病合併妊娠
4)多胎妊娠
5)その他
原因により治療法は異なりますが、高度の羊水過多症には羊水穿刺による羊水除去を行うこともあります。
Q31.羊水の量が少ないと言われました。
A.
子宮底長が過少であれば羊水過少を疑います。
AFPまたはMVP<2(cm)、またはAFI<5(cm)を羊水過少としています。
AFP、MVP、AFIについては前項の産科Q30.をご覧ください。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020では、原因として以下を挙げています。
1)母体側要因:妊娠高血圧症候群、抗リン脂質抗体症候群、膠原病、血栓症など胎盤機能不全を起こしやすい病態、母体の解熱鎮痛剤内服、ACE阻害薬。アンギオテンシン湯様態阻害薬内服等
2)胎児側要因:腎無形成、腎異形成糖の無機能腎や尿産生不良となる腎形成異常、閉塞性尿路疾患等の尿排出障害、染色体異常、胎児発育不全、胎児死亡、過期妊娠等
3)胎盤・臍帯。卵膜要因:破水、胎盤梗塞・血栓、双胎間輸血症候群、持続的な胎盤出血等
4)その他、原因不明
Q32.トキソプラズマ感染について
A.
広島市の妊娠初期検査ではトキソプラズマ検査が組み込まれており、質問を受けます。
トキソプラズマは、人畜共通寄生虫のひとつで、ネコ科動物を終宿主とし、ヒトを含む哺乳動物や鳥類などの恒温動物を中間宿主としています。
胎児感染を起こすと、水頭症・頭蓋内石灰化・小頭症・腹水・肝脾腫・胎児発育遅延を起こすことがあります。
従って、妊娠成立後の初感染が疑われる場合は、スピラマイシン投与による加療をすることとなります。
また、感染予防のための注意は必要ですので、以下のことに気をつけてください。
1)食事からの感染予防
肉食は十分に加熱して食べる。(調理前に数日間冷凍するとより効果が高い)牛トロ、レバ刺し、馬刺し、鳥刺し、ユッケ、タルタルステーキなど生肉だけでなく、加熱不十分な肉、生ハムや生サラミからも感染する。特に野生動物の肉を用いた「シビエ」料理は、しっかりと加熱し調理する。
野菜や果物はよく洗うかきちんと皮をむいて食べる。
生肉や洗っていない野菜や果物を扱った調理・食事用具・手指は十分な洗剤と温水で洗浄する。
猫をキッチン、食卓に近づけない。
2)環境からの感染予防
飲料水以外は飲まない。
ガーデニングなどで土を触る際は手袋を着用し、土を触った後は手指を石鹸と温水で洗浄する。
子供にも手指洗浄の重要性を教育する。
砂場にはカバーをかける。
妊娠中に新しい猫を飼わない。
飼い猫はできるだけ部屋飼いにし、食餌はキャットフードを与える。
猫のトイレの砂は妊婦以外のものが毎日交換する。
Q33.妊娠中の新型コロナワクチン接種について
A.
妊娠中の医療従事者や若い方への新型コロナワクチン接種が進むにつれて、妊娠中の新型コロナワクチン接種についての質問をよく受けるようになりました。
これについては2021年4月21日のブログにも記載していますが、こちらのコーナーにも転記します。
日本産婦人科感染症学会、日本産科婦人科学会では、妊婦に対しての十分な知見がなく、各国で見解が分かれているとされています。米国のACIP(ワクチン接種に関する諮問委員会)は、妊婦を除外すべきではないとし、イスラエルでは積極的な接種対象としています。一方で、英国やカナダでは十分な臨床データがないことから推奨していません。
COVID-19mRNAワクチンの動物の生殖に関する研究はまだ完了しておらず、中・長期的な副反応についても現時点では不明なことより、現時点では妊婦に対する安全性、特に中・長期的な副反応、胎児および出生児への安全性は確立していないとされています。
「流行拡大の現状を踏まえて、妊婦をワクチン接種から除外することはしない。」、「感染リスクが高い医療従事者、重症化リスクがある可能性がある肥満や糖尿病など基礎疾患を合併している方はワクチン接種を考慮する。」という曖昧な表現になっています。
最終的には産婦人科主治医とよく話し合って決めてくださいということになりますが、厚生労働省のサイトでは「妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の方も、新型コロナワクチン接種することができます。」と記載されています。
私は、妊娠初期の器官形成期(妊娠12週まで)を除いては、接種を積極的にしてもよいと考えています。
また、2021年4月23日に米国疾病対策センター(CDC)は、新型コロナワクチンに妊婦への接種を推奨すると明らかにしました。
CDCの研究者らが21日に大規模な調査の結果を米医学誌New England Journal of Medicineに掲載し、ファイザー製ワクチンを接種した3万5千人以上の妊婦での副反応や、3900人以上の妊娠の経過を調査したころ、ワクチン接種によって妊婦や新生児の安全性に懸念が増すことは無かったとされました。
これを受け、CDCでは妊婦へのワクチン接種を推奨すると判断されました。
また、2021年6月17日に日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の連名で、妊産婦の皆様に新型コロナウイルス(メッセンジャーRNA)ワクチンについてのリーフレットが発出されました。すでに多くの接種経験のある海外の妊婦に対するワクチン接種に関する情報では、妊娠初期を含め妊婦と胎児双方を守り、母体や胎児に何らかの重篤な合併症を発生したという報告もないとのことです。これを受けて、日本においても、希望する妊婦さんはワクチンを接種することができるとされました。
さらには、2021年8月14日に新型コロナウイルス(メッセンジャーRNA)ワクチンについて(第2報)のリーフレットが発出されました。「わが国においても、妊婦さんは時期を問わずワクチンを接種することをお勧めします。」とより積極的にワクチン接種を推奨する表現となりました。また、妊婦が感染する場合の約8割は夫やパートナーからのため、妊婦の夫やパートナーの方へのワクチン接種も強く勧められています。
COVID-19ワクチン接種を考慮する妊婦さんならびに妊娠を希望する方へ(日本産婦人科感染症学会、日本産科婦人科学会)
Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons(NEJM)
新型コロナウイルス(メッセンジャーRNA)ワクチンについて(日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会)
Q34.異所性妊娠(子宮外妊娠)について
A.
異所性妊娠は全妊娠の1〜2%程度の頻度で発症する比較的多い疾患です。
妊娠反応陽性で、超音波検査で子宮腔内に胎嚢(GS)が確認できない場合は、ごく初期の正常妊娠、流産、異所性妊娠の三者の鑑別が必要となりますが、早期の段階で診断をつけることは無理です。
産婦人科診療ガイドライン産科編2020においても、妊娠4〜5週における無症状の異所性妊娠の診断は極めて困難であるため、上記三者の可能性があることを患者に伝え、1〜2週後に経膣超音波を行うことが勧められると記載されています。
不正出血の症状があっても、妊娠初期では流産と異所性妊娠の鑑別は困難です。
正常の妊娠でも、初診時に胎嚢が見えず、1週間後にはっきりと胎嚢が確認できるケースがよくあります。
妊娠初期は数日間で劇的な変化が起こります。
初診時に診断がつかず、数日後に異所性妊娠の診断がつくことはよくあります。
当院では初診時に妊娠反応陽性で子宮内に胎嚢が確認できない場合は、1週間後の再検査を指示しています。
1週間後の再検査を待たずに症状が急変し、他院にて異所性妊娠の診断を受けることがあります。
このような場合に、初診時に異所性妊娠の診断がつかなかったため、患者やその家族から初診時に見逃した、誤診をしたと責められることが多々あります。
異所性妊娠の診断がつく数日前には分からないことはあり得ます。
初診時に診断ができなかったことは事実ですが、決して見逃した、誤診したのではなく初診時はまだ診断がつけられない状態だったということです。
妊娠初期は数日間で急激な変化が起こることがあることが一般的には理解できないかもしれませんが、産婦人科医の間では共通の認識です。
他院で診断がつけられなかった異所性妊娠を発見した場合、前医が見逃した、誤診したという産婦人科医はいないと思います。
異所性妊娠は初診時の所見では診断がつかず、経過をみないと診断がつかないことが多いことをご理解ください。
また、悪性腫瘍などは早期発見による治療で治すことはできますが、異所性妊娠は早期発見できたとしても治すことはできず経過を見ながら手術を決定することとなります。
Q35.妊婦へのRSウイルスワクチン接種
A.
RSウイルス(RSV)は乳幼児における下気道感染の代表的な原因のひとつです。
感染すると、ウイルスの潜伏期間の4〜5日後から数日間にわたり発熱や鼻汁、せき、のどの痛みなどかぜの症状が続きます。呼吸器の炎症が進行し細気管支炎や肺炎を発症する場合もあります。
RSV感染症は世界規模でみると1歳未満の急性下気道炎による死亡の1/3を占めています。
早産・慢性肺疾患・免疫不全を有する児で重症化リスクが高いとされています。
正常に産まれた児でも出生後早期から感染し、生後1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%が初感染し、その後は終生再感染を繰り返します。
日本では毎年2歳未満の12万人前後がRSV感染症の診断を受けています。
診断を受けた児の約25%が入院加療となっています。
問題となるのが、入院患者の40%が生後6ヶ月未満であり、入院患者の90%はRSVの重症化リスクを有していないことです。
乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の50〜90%がRSウイルス感染症によるとされています。
合併症として無呼吸、急性脳症などがあり、後遺症として反復性喘鳴(気管支喘息)があります。
新生児や乳幼児では、ウイルスや細菌等の病原微生物に対する抵抗力(免疫)が未発達なため、様々な感染症にかかりやすい状態で、感染すると症状が重くなる可能性があります。
新生児や乳幼児にワクチンを接種してRSV感染の予防することは困難です。
妊婦に対してワクチン接種すると抗体量の増加があり、この抗体は胎盤を経由して胎児に移行します。
このことを経胎盤的抗体移行(maternal immunization)と呼んでいます。
諸外国では1歳未満の百日咳は重症化しやすく、特に月例3ヶ月未満では死に至ることもあり、百日咳ワクチンの妊娠中の母体への投与が推奨されています。
日本では、百日咳ワクチンの妊娠中の母体への接種は一般的ではありません。
2024年6月から、日本ではRSウイルスワクチン(アブリスボ筋注用)が発売となります。
効能または効果は、「妊婦への能動免疫によ新生児及び乳児におけるRSウイルスを原因とする下気道疾患の予防」「60歳以上の者におけるRSウイルスによる感染症の予防」となっています。
妊娠24〜36週の妊婦に1回接種となっていますが、妊娠28〜36週の接種が推奨されています。
本剤投与により生後6ヶ月までの有効性が検証されています。
臨床試験では生後180日以内のRSVによる下気道疾患を約51%減少(1.6%vs3.4%)させ、生後180日以内の重症例を約69%減少(0.5%vs1.8%)させています。
RSウイルス感染症の重症化抑制薬として、抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤のパリビスマブがありますが、適応症が基礎疾患を有する児や早産児に限定されています。入院の大部分を占める基礎疾患のない正期産児には使用することができない事が課題となっています。この課題の解決法として、妊娠中の妊婦に対するワクチン投与が有効な手段と考えられます。
また、RSウイルス母子免疫ワクチンを接種している場合は、抗体薬を出生直後乳児に投与することは原則的に行いませんので、児が入院となった場合は小児科医師に母体へのワクチン接種を伝えることが重要です。
お母さんからお腹の中の赤ちゃんへの贈り物・プレゼントとして、妊娠中のRSワクチン接種を考えてみてはどうでしょうか。
婦人科Q&A
| マンモグラフィ | 子宮がん検診 | 子宮頸がん | 子宮体がん |
| 子宮肉腫 | ミレーナ | 子宮内膜増殖症 | 異形成 |
| 細胞診結果 | ヤーズフレックス | プラセンタ療法 | 乳がんサブタイプ |
| HPVワクチン | 子宮体がん検診 | HPVワクチン副反応 | 乳がん視触診 |
| OC/LEP | 連続投与 | ブレスト・アウェアネス |
Q1.乳がん検診にマンモグラフィが必要な理由は?
A.
2004年より、市民健診では視触診に加えてマンモグラフィを施行するようになりました。
さらには2019年からは市民検診では視診・触診は廃止となり、マンモグラフィのみの検診となりました。
それだけマンモグラフィが必須の検査であるということです。
対象は、40歳以上となっています。
有効性評価の結果から、乳がん検診ではマンモグラフィを併用することが推奨されます。
2年に1回の検診でも毎年検診を受けた場合と同じ有効性が示されており、2年に1回の検診をお願いしています。
マンモグラフィによる放射線被爆はほんのわずかで、東京からニューヨーク間の飛行機の中で受ける宇宙からの自然の放射線量の約半分です。
この危険性は、飛行機での160kmの旅行、自動車での24kmの旅行、タバコ1/4本の喫煙と同等の危険率で極めて低いものです。
当院ではマンモグラフィ検診は随時いつでもできますので、ご希望の方はお申し付けください。
Q2.子宮がん検診が20歳から必要な理由は?
A.
2004年から子宮頸がん検診の対象が20歳以上となりました。
検診間隔は2年に1回となっています。
子宮頸がん検診は非常に有効で、科学的に進行がんを防ぎ死亡を減らす効果が証明されています。
以前は毎年の検診を行っていましたが、検診間隔を延ばして2〜3年に1回の検診でも有効であるデータが多く出ています。
検診結果が3回連続して異常を認めない場合には、3年に1回としている国もあります。
月経のある方は、正しい判定のために月経終了後3〜7日の間に検診を受けるのが理想です。
しかしながら検診を受ける機会を逃さないために、仕事などで都合がつかない場合は月経中でも構いません。
子宮頸がんの原因としてHPV(ヒトパピローマウィルス)が関与していることが分かってきました。
このウィルス感染は、性交によって起こることも分かっています。
現在では、わが国でもHPVワクチン接種が可能となりました。 HPV感染を予防することができれば、子宮頸がんは激減することが予測されています。
早期発見のためには性経験のある年齢から子宮がん検診受診が必要です。
性経験のある女性は、年齢にこだわらず子宮がん検診を受けることが必要です。
Q3.子宮頸がんについて
A.
子宮がんには、子宮頸がんと子宮体がんがあります 。
子宮頸がんは、子宮と膣の境目の部分すなわち子宮の入り口(赤ちゃんの出口)にできるがんです。
婦人科がんの中で最も多いのが、子宮頸がんです。
発症には、HPVウイルス感染が関与していることが分かってきています。
病理組織学的には、扁平上皮がんが最も多く、次に腺がん、その他と続きます。
子宮頸がんは30歳から40歳代が多く、前がん病変と早期がんは20歳から30歳代に多いため、Q2.で示したように子宮がん検診の対象者は20歳からとなっています。
初期の子宮頸がんでは自覚症状がないため、検診により発見することが多いがんです。
がんが進行するに従い、性交時出血、帯下の異常がみられるようになり、さらに進行すると悪臭のある膿血性帯下、不正性器出血、下腹痛などが出てきます。
Q4.子宮体がんについて
A.
子宮体がんは、子宮内の赤ちゃんが育つ空間を覆っている子宮内膜から発生します。
子宮頚がんはHPVウイルスが原因ですが、子宮体がんはウイルスには関係なくエストロゲン(女性ホルモン)の関与が主として原因となります。
集団検診などの一般的な子宮がん検診では、子宮体がん検診は含まれていないことが多いです。
市民検診や会社検診では子宮頸がん検診しかしないことが多く、子宮がん検診を受けたら子宮頚がんも子宮体がんも異常ないものだと誤解しないように注意が必要です。
子宮体がんの場合は、ごく初期の段階から不正出血があることが多いのが特徴です。
不正出血があってから検診を受けても初期の段階で発見されることが多いので、不正出血があれば必ず子宮体がんの検診を受けることが重要です。
Q5.子宮肉腫について
A.
子宮体部にできる悪性腫瘍に、がんの他に肉腫があります。
子宮肉腫は婦人科悪性腫瘍の中で非常にまれで、子宮体がんの2〜5%です。
子宮頚部にできることもありますが、ほとんどは子宮体部の子宮の筋肉から発生します。
子宮の筋肉から発生する良性疾患として子宮筋腫がありますが、子宮筋腫と子宮肉腫の区別が非常に難しいことがあります。
急速な子宮の増大、とくに閉経後に増大する場合は子宮肉腫を疑います。
症状としては特別なものはありませんが、不正性器出血、腹痛、下腹部の違和感などがあります。
Q6.ミレーナ(子宮内黄体ホルモン放出システム)について
A.
ミレーナ(子宮内黄体ホルモン放出システム)は、子宮内リングの一つです。
ミレーナには器具本体にノボノルゲストレルという黄体ホルモンが添加されており、その作用で子宮内膜が薄くなります。
月経は子宮内膜が剥がれ落ちて起こる現象ですので、薄くなった内膜がはがれて月経になるために月経の量が随分少なくなり、月経痛を軽減する効果があります。
この効果が認められ、2014年9月に薬価基準収載され保険適応となりました。
鎮痛剤が効かないほどの月経痛で悩んでいる方や、月経のたびに大出血して貧血を繰り返す、夜用ナプキンでも間に合わないぐらいの月経血量があるなどの過多月経でお悩みの方には、非常に良い治療法だと考えます。
今まではLH-RH誘導体やLEP(低用量ピル)にて過多月経の治療を行っていましたが、LH-RH誘導体では強力にエストロゲンを抑制するため更年期症状や骨粗しょう症になる、LEP(低用量ピル)では血栓症の重篤な副作用を起こす可能性がありました。
ミレーナではこれらの副作用がないため、特に血栓症の心配で治療が受けられなかった方には非常に有効な治療法です。
また、ピルのように毎日服用する煩わしさもありません。
挿入後5年間は治療効果がありますので、5年毎の入れ替えで治療ができます。
薬価は26,984.30円で約27,000円となっています。
保険適応であれば3割負担となりますので器具代だけで自己負担は約8,100円、それで5年間有効ですので1年間で約1,600円の費用で済みます。
保険適応があるかどうかは主治医の判断となります。
月経の量が多くて困っている方は、ご相談ください。
ミレーナ(バイエルウィメンズヘルス)
Q7.子宮内膜増殖症について
A.
子宮内膜増殖症は、子宮体癌取扱い規約による定義では「子宮内膜腺の過剰増殖」とされています。
子宮内膜増殖症は、上皮細胞の細胞異型の有無や腺構造の異常の程度により、1)単純型子宮内膜増殖症、2)複雑型子宮内膜増殖症、3)単純型子宮内膜異型増殖症、4)複雑型子宮内膜異型増殖症の4つに分類されます。
この中には自然に正常子宮内膜に戻るものもありますが、子宮体癌に進行するものもありますので慎重な取扱いが必要です。
子宮体癌への進展率は、細胞異型を伴わない子宮内膜増殖症からは1〜3%と低いのですが、複雑型子宮内膜異型増殖症からは20〜30%と報告されています。
従って、細胞異型を伴わない子宮内膜増殖症では3ヶ月ごとの細胞診ならびに組織診による経過観察が基本ですが、子宮内膜異型増殖症においては積極的な治療が必要と考えます。
子宮体癌に進展する確率の高い異型内膜増殖症においては、子宮全摘出術が最も確実な治療法です。
今後の妊娠を希望される方には、高用量の黄体ホルモン療法により子宮を温存し妊娠可能な例もあります。高用量黄体ホルモンが有効でも、その後の再発や子宮体癌に進行する例もあり子宮を温存した場合は十分に注意をしながら経過観察する必要があります。
また、子宮内膜増殖症の診断で子宮全摘出を行い、術後の病理組織検査で子宮体癌と診断される例が約40%あるとの報告もあります。
術前に診断不可能な子宮体癌を合併している子宮内膜増殖症もあることより、特に異型子宮内膜増殖症で子宮温存の必要性がない場合は、子宮全摘出術を勧めることは妥当と考えます。
異型子宮内膜増殖症と診断され今後妊娠する希望のない場合は、子宮全摘出術を考慮された方がよいと考えます。
Q8.CIN1/2(軽度/中等度異形成)について
A.
CINとはCervical Intraepithelial Neoplasiaの略で、子宮頚部上皮内腫瘍のことです。
組織診により、CIN1(軽度異形成)、CIN2(中等度異形成)、CIN3(高度異形成)の3段階に分けます。
CIN1(軽度異形成)がCIN3(高度度異形成)に進展する可能性は12〜16%程度です。
組織診で診断が確定されたCIN1はフォローが必要です。
CIN1の殆どは自然消失し、特に30歳未満では約90%で消失します。
CIN1では、原則として治療の必要はなく定期検診でよろしいです。
CIN2(中等度異形成)がCIN3(高度異形成)以上の高度病変に進展する可能性は25%程度です。
CIN2においても、30歳未満や妊婦では消失することが多いとされています。
CIN2でも原則として治療の必要はなく、定期検診で可です。
定期検診は、3〜6カ月毎の細胞診を行います。
CIN2では、原則としてコルポスコピーを併用し慎重な経過観察が必要です。
Q9.子宮頸部細胞診結果について
A.
以前は子宮がん検診の結果をクラス分類で、クラス1・2は良性、クラス3は良性と悪性の間、クラス4・5は悪性として数字の1〜5までで表していました。
最近はこのクラス分類での結果表示を行わず、ベセスダシステムで報告するようになっています。
ベセスダシステムでは、以下のように略語で結果報告となります。
NILMの結果であれば異状なし、それ以外の結果は何らかの精密検査を要すると理解してください。
| 略語 | 推定病変 | 運用 |
| NILM | 非腫瘍性所見、炎症 | 定期検査 |
| ASC−US | 軽度扁平上皮内病変の疑い | HPV検査 |
| ASC−H | 高度扁平上皮内病変の疑い | コルポ・生検 |
| LSIL | HPV感染、軽度異形成 | コルポ・生検 |
| HSIL | 中等度異形成、高度異形成、上皮内癌 | コルポ・生検 |
| SCC | 扁平上皮癌 | コルポ・生検 |
Q10.ヤーズフレックス錠について
A.
月経困難症・過多月経の治療として、LEP(低用量卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤)を使用しています。これらの薬剤は4週間に1度で消退出血(月経のような出血)を起こす方法が基本となっています。
2017年4月に、ヤーズフレックス配合錠が使用可能となりました。
この薬剤は成分は今までのヤーズ配合錠と全く同じですが、120日間連続して服用可能な薬剤です。もちろん薬価基準収載医薬品で、保険診療可能な薬剤です。
120日間連続服用中は出血が起こらず、1年間に3回ほど消退出血(月経のような出血)が起こることとなります。
毎月の排卵後に子宮内膜が肥厚して妊娠の準備がおき、妊娠成立がないと内膜が剥がれて月経が来ます。そして翌月に再度妊娠の準備をおこし、妊娠成立が無ければ再度月経を起こすことを繰り返しています。妊娠の希望が無ければ、わざわざ毎月妊娠の準備をおこして辛い月経を迎える必要はありません。
従って妊娠の希望が無く月経時に起こる下腹痛・腰痛・疲労感・イライラ・抑うつ症状などで悩んでいる方は、毎月の出血を避ける方法もよいと考えます。
ヤーズフレックス(バイエルウィメンズヘルス)
Q11.プラセンタ療法について
A.
当院では閉経後のエストロゲン欠乏に伴う諸症状や疾患の予防のために、ホルモン補充療法(Hormone Replacement Therapy:HRT)を積極的に行っています。
プラセンタ療法をしないのかとの質問をよく受けます。
プラセンタ療法とは胎盤抽出物を用いた治療で、日本では保健適応のある薬剤が2つあります。
一つは「ラエンネック」で、効能・効果は慢性肝疾患における肝機能の改善となっており、更年期障害の治療の適応はありません。もう一つは「メルスモン」で、効能・効果は更年期障害、乳汁分泌不全となっています。しかしながら、臨床現場において「メルスモン」を使用する施設は殆どないと思われます。
両薬剤ともにホルモン作用はないと考えられています。
また、特定生物由来製品のため、献血や臓器提供制限があり、使用記録を20年間保存する義務もあります。
HRTの代用とはならないため、当院ではプラセンタ療法はしておりません。
ホルモン補充療法ガイドライン2017年度版においても、「プラセンタ療法は更年期障害に対するHRTの代用とはならない。」と記載されています。
また、マスコミ等でサプリメントとしての「プラセンタ」もよく宣伝されています。宣伝する自由はありますが、科学的根拠は少ないと思われます。
医師仲間のメーリングリストにてプラセンタ療法についての話題がありました。
当院の考えを示しましたので、お知らせします。
> 実は、とある女性の患者様から「貴院にてプラセンタの定期投与を受けたい」
とのお申し出がありました。
の質問に対しての当院の回答です。
当院でもプラセンタについての相談をよく受けますが、当院ではプラセンタ治療はお断りしています。
ホルモン補充療法ガイドライン(2017年度版)では、
CQ502 プラセンタ療法は更年期障害に対するHRTの代用となるか?
Answer HRTの代用とはならない
推奨レベル :1(強い推奨)
エビデンスレベル :+−−−(Very low)
となっています。
ホルモン補充療法の代用にはなりません。
効能・効果は
ラエンネック:慢性肝疾患における肝機能の改善
メルスモン:更年期障害、乳汁分泌不全
となっています。
ラエンネックは更年期障害には適応外使用となり、更年期障害治療にメルスモンを選択する婦人科医は極めて稀です。
また、特定生物由来製品であるため、献血や臓器提供制限があることや、未知の感染性因子を含んでいる可能性が否定できない等の説明が必要ですが、十分な説明がないまま「更年期障害に効く」「若返る」等の謳い文句で投与を受けているケースがよくあります。
当院に今回のような患者が来院された場合は、特定生物由来製品であり、エビデンスレベルが非常に低い理由でお断りしています。
Q12.乳がんサブタイプについて
A.
乳がんルミナルAという診断を受けたが、内容がよく分からないと質問を受けることがあります。
乳がんの薬物療法として、ホルモン療法・化学療法・分子標的治療があります。
それぞれの治療の適応は、ホルモン受容体の有無やHER2陽性かで決めていましたが、近年ではサブタイプ分類という考え方が出ています。
サブタイプ分類はがん細胞の性質で分類し腫瘍の性質に合わせた治療法を選択します。
ルミナルAはサブタイプ分類の一つです。
| サブタイプ分類 | ホルモン受容体 | HER2 | Ki67 | |
| ER | PgR | |||
| ルミナルA型 | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 低 |
| ルミナルB型(HER2陰性) | 陽性又は陰性 | 弱陽性又は陰性 | 陰性 | 高 |
| ルミナルB型(HER2陽性) | 陽性 | 陽性又は陰性 | 陽性 | 低〜高 |
| HER2型 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | ー |
| トリプルネガティブ | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ー |
A.
2013年4月にHPVワクチンは予防接種法に基づき定期接種化されました。
しかしながら接種後に慢性疼痛や運動障害などの多様な症状が報告され、わずか2か月後の2013年6月に接種の積極的勧奨が中止されたままとなっています。
これは自治体等から接種対象者宛に、接種時期をお知らせしたり、個別に接種を奨めるような「積極的勧奨」を中止しているもので、定期接種としての位置づけに変化はありません。
当院近くの自治体担当者から「ワクチン接種しなくても、子宮がん検診を受ければいいのでは」と説明があったと保護者から相談を受け、自治体担当者の認識も間違っていることに驚きました。
積極的勧奨中止をワクチン接種中止と捉えている方がいらっしゃいますが、現在でも定期接種の位置づけに変わりはありません。
当院ではHPVワクチン接種を推奨しており、ワクチン接種と子宮がん検診受診を組み合わせることにより、子宮頸がんは予防できるものと思っています。
最近、ワクチン接種該当年齢の子供様をお持ちの保護者からよく相談を受けるようになりました。
大切なお子様を子宮頸がんから守るため、正しい理解で判断してください。
正しい理解のために、日本産科婦人科学会や厚生労働省から情報発信されています。
日本産科婦人科学会
子宮頸がん予防についての正しい理解のために
Part1 子宮頸がんとHPVワクチンについての正しい理解のために(第3.1版 2020年7月21日)
Part2 子宮頸がん検診の最新の知識(初版 2020年7月10日)
Part3 HPVワクチン最新情報(浸潤子宮頸がんの減少効果や9価HPVワクチンについて)(初版 2021年1月8日)
厚生労働省
リーフレット(概要版)
リーフレット(詳細版)
リーフレット(受けた後版)
Q14.子宮体がん検診について
A.
子宮頸がん検診を受けるときに、ついでに子宮体がん検診を希望する方や子宮体がん検診はしなくてもよいのかとの質問をよく受けます。
産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編2020では、わが国の子宮体がんのスクリーニングは、子宮体がんの高危険群、すなわち最近6か月以内に不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)および褐色帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した女性を対象に行われており、本来の検診とは趣を異にしている。年齢を考慮せずに無症状女性にあまねく検診をすることは有効性が確認できていないことおよび費用対効果の点から容認されないと記載されています。
当院では、不正性器出血・月経異常・褐色帯下のある方、超音波検査で子宮内膜肥厚所見のある方、子宮体がんの高リスク因子(未婚、不妊、閉経後、初婚・初妊年齢が高い、妊娠・出産数が少ない、30歳以降の月経不規則、エストロゲン服用歴、糖尿病の既往、高血圧の既往、肥満、など)のある方を対象に、必要性があると考えられる場合のみに子宮体がん検診を施行しています。
Q15.9価HPVワクチンの副反応について
A.
9価HPVワクチンの副反応について、今までの2価・4価ワクチンと差があるのかとの質問をよく受けます。
添付文書の副反応の報告を見ると差はありません。
6か月間で3回接種が必要なことを含め、今までの2価・4価ワクチンと比べて変わりはありません。
4価ワクチン(ガーダシル)
| 種類・頻度 | 10%以上 | 1~10%未満 | 1%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 全身症状 | 発熱 | 無力感、悪寒、疲労、倦怠感 | ||
| 局所症状(注射部位) | 疼痛、紅斑、腫脹 | 掻痒感、出血、不快感 | 硬結 | 血腫 |
| 精神神経系 | 頭痛 | 失神(硬直間代運動を伴うことがある)、不動性めまい | ||
| 筋・骨格系 | 四肢痛、筋骨格硬直 | 関節痛、筋肉痛 | ||
| 消化器 | 下痢、腹痛 | 嘔吐、悪心 | ||
| 血液 | リンパ節症 | |||
| 感染症 | 蜂巣炎 | |||
| 臨床検査 | 白血球増加 |
| 10%以上 | 1~10%未満 | 1%未満 | 頻度不明 | |
|---|---|---|---|---|
| 全身症状 | 発熱 | 無力感、悪寒、疲労、倦怠感 | ||
| 局所症状(注射部位) | 疼痛、腫脹、紅斑 | 掻痒感、出血、熱感、腫瘤、知覚消失 | 内出血、血腫、硬結 | |
| 精神神経系 | 頭痛、間隔麻痺 | 失神(硬直間代運動を伴うことがある)、不動性めまい | ||
| 筋・骨格系 | 四肢痛 | 関節痛、筋肉痛 | ||
| 消化器 | 悪心 | 腹痛、下痢 | 嘔吐 | |
| 血液 | リンパ節症 | |||
| 感染症 | 蜂巣炎、インフルエンザ | |||
| 呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 口腔咽頭痛 |
Q16.乳がん検診に視触診は必要ですか?
A.
結論からいうと、当院では厚生労働省の指針に基づき、視触診は行っていません。
がん検診の目的は、がんを見つけることだけではありません。
検診の対象となる人たち(集団)の死亡率や罹患率を低下させることが、がん検診の目的です。
検診により治療効果のないがんや、治療が不要ながんがいくらたくさん発見されても、死亡率低下の効果はないため検診としての意味はありません。
これまでの研究により、胃がん・肺がん・乳がん・子宮頸がん・大腸がんの5つのがんは、それぞれ特定の検査法による検診で早期の発見でき、さらに治療を行うことで死亡率が低下することが科学的に証明されています。
科学的に有効と証明されたがん検診は以下のとおりです。
| 対象臓器 | 効果のある検診方法 |
|---|---|
| 胃 | 胃X線検査 胃内視鏡検査 |
| 子宮頸部 | 子宮頸部細胞診 |
| 乳房 | マンモグラフィ(乳房X線) |
| 肺 | 胸部X線とハイリスク者に対する喀痰細胞診の併用 |
| 大腸 | 便潜血検査 |
乳がん検診については、厚生労働省のがん予防重点教育及び検診実施のための指針(2016年2月4日一部改正)で、「乳がん検診の検診項目は、問診及び乳房エックス線検査とする」と明記されました。
2000年に導入した視触診+マンモグラフィから、視触診を廃止してマンモグラフィ単独検診に舵が切られました。
がん検診には、市町村が実施する対策型検診と人間ドックなどの任意型検診があります。
| 対策型がん検診(住民検診型) | 任意型がん検診(人間ドック型) | |
|---|---|---|
| 基本条件 | 当該がんの死亡率を下げることを目的として、公共施策として行うがん検診 | 対策型がん検診以外のもの |
| 検診対象者 | 検診対象として特定された集団構成員の全員(一定の年齢範囲の住民など)ただし、無症状であること。症状があり、診療の対象となる者は該当しない | 定義されない。ただし、無症状であること。症状があり、診療の対象となる者は該当しない |
| 検診方法 | 当該がんの死亡率減少効果が確立している方法を実施する | 当該がんの死亡率減少効果が確立している方法が選択されることが望ましい |
| 利益と不利益 | 利益と不利益のバランスを考慮する。利益が不利益を上回り、不利益を最小化する | 検診提供者が適切な情報を提供したうえで、個人レベルで判断する |
| 具体例 | 健康増進事業による市町村の住民対象のがん検診(特定の検診施設や検診車による集団方式と、検診実施主体が認定した個別の医療機関で実施する個別方式がある) | 検診機関や医療機関で行う人間ドックや総合健診、保険者が福利厚生を目的として提供する人間ドック |
がん検診ガイドラインでは、
マンモグラフィ単独法(40〜74歳):推奨グレードB
マンモグラフィと視触診の併用法(40〜64歳):推奨グレードB
マンモグラフィ単独法及びマンモグラフィと視触診の併用法(40歳未満):推奨グレードI
視触診単独法:推奨グレードI
超音波検査(単独法・マンモグラフィ併用法)推奨グレードI
推奨グレードB:利益(死亡率減少効果)が不利益を上回るがその差は推奨Aに比し小さいことから、対策型検診・任意型検診の実施をすすめる
推奨グレードI:死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であるため、利益と不利益のバランスが判断できない。このため、対策型検診として実施することは勧められない。任意型検診として実施する場合は、効果が不明であることと不利益について十分説明する必要がある。適切な説明に基づき、個人レベルで検討する
となっています。
以上の理由から、対策型がん検診の広島市民検診ではマンモグラフィ単独法となり、視触診は廃止されました。
また、マンモグラフィ検査は痛みを伴うため、超音波検査での検診を希望される方がいます。
超音波検査では乳がんの死亡率減少効果の有無を判断する証拠がないため、当院ではマンモグラフィ検査をお勧めしています。もちろん、マンモグラフィ所見で異常があれば、超音波検査も施行しています。
Q17.OCとLEPはどこが違うのですか?
A.
ピルの処方を受けるときに、OCとかLEPという言葉をよく聞きますが、どこが違うのかと思われます。
OCは、oral contraceptiveの略語で、経口避妊薬または低用量経口避妊薬を表します。
LEPは、low dose estorogene-progestinの略語で、低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤を表します。
両者は実質的には同じ薬剤です。
OCは文字通り、避妊を目的とする薬剤で、自費診療となります。
一方、ピルを服用すると月経困難症や子宮内膜症に伴う疼痛などを緩和する作用もあり、治療を目的として保険診療として処方される薬剤をLEPとしています。
これらの薬剤服用による重篤な副作用として、エストロゲン由来のVTE(静脈血栓塞栓症)とプロゲスチン由来の脂質代謝への影響の問題があります。
この副作用軽減のため、アメリカ食品医薬局(FDA)は1970年にEE(エチニルエストラジオール)の含有量を50マイクログラム未満にすべきであるとの勧告が出されました。
含有されているEEが50マイクログラムのものを中用量、それ未満のものを低用量としています。
LEPの中にはEEが20マイクログラムの超低用量製剤もあり、NET(ノルエチステロン)/EE製剤(低用量・超低用量)、DRSP(ドロスピレノン)/EE製剤(超低用量)、LNG(レボノルゲストレル)/EE製剤(超低用量)とEE含有量やプロゲスチンの違いから選択可能です。
また、服用方法にも周期服用(毎月出血を起こす方法)と連続服用(3〜4ヶ月おきに出血を起こす方法)があります。
どの薬剤を選択するかは主治医と相談して決定することとなります。
Q18.OC・LEPの周期投与と連続投与について
A.
Q10.ヤーズフレックス錠についてにおいて、2017年4月から120日間連続服用できる方法が可能となったことを説明しました。
従来はOC・LEPの服用法として、21日間実薬を内服し、7日間偽薬内服もしくは休薬を繰り返して毎月の出血を起こす方法が標準でした。
しかしながら、毎月出血を起こさせることに明らかな健康上の利点はなく、出血が起こる時に頭痛や気分変調などを訴える方も多くいます。
休薬期間の出血時に起こる症状をホルモン関連症状とよび、骨盤痛・頭痛・腹部膨満感・乳房痛なと様々な症状を呈します。
このホルモン関連症状を回避する目的で、毎月の出血を起こす方法(周期投与)を避けて長期間服用する方法(連続投与)が考案されました。
日本では、3ヶ月に1回と4ヶ月に1回に出血を起こす方法が認可されています。海外では1年以上連続して服用して1年以上出血を起こさない方法も用いられています。
OC・LEPガイドライン2020年度版でも、連続投与についての記載が多くされています。
CQ102.連続投与についての説明は?
A.連続投与により、毎月の消退出血と休薬に伴う諸症状を回避することができる.(C)
CQ103.周期投与と連続投与の比較についての説明は?
A.1.安全性は同等である.(C)
2.連続投与では周期投与と比較して、休薬期間に頭痛や気分不調などが起こりにくい.(C)
3.連続投与では周期投与に比較して、出血日数が少ない.(C)
推奨レベル(C):(実施すること等が)考慮の対象となる
以上のように、最近は周期投与から連続投与へと流れが変わってきています。
Q19.ブレスト・アウェアネスについて
A.
これまでは乳がん検診手段として自己検診(breast self-examinatin:BSE)という用語が使用されていました。
BSEでは、手技や手順は確立されておらず、死亡率減少の科学的根拠がなくかえって偽陽性による不利益の増加が認められました。
2021年10月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が一部改正されました。その中で、自己触診の文言が削除され、「ブレスト・アウェアネス」の用語が採用されました。
アウェアネス(Awareness)とは、「意識する」「意識向上」と直訳されます。
ブレスト・アウェアネスは、「乳房を意識する生活習慣」と定義され、実践するポイントとして以下の4つがあります。
1)自分の乳房の状態を知る。
2)乳房の変化に気をつける。
3)変化に気付いたらすぐに医師に相談する。
4)40歳になったら2年に1回乳がん検診を受ける。
自分の乳房の状態に日頃から関心を持ち、乳房を意識して生活することで、乳癌の早期発見につながります。
ブレスト・アウェアネスで乳癌を早期発見!(広島市)
ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)のすすめ(乳がん検診の適切な情報提供に関する研究)
乳がん検診について教えてください。(患者さんのための乳癌診療ガイドライン2019年版)
内科Q&A
| ノロウイルス | 膀胱炎 | 過活動膀胱 | 便秘症 |
| 急性気道感染症 |
Q1.ノロウイルス感染症について教えてください。
A.
寒くなる11月頃よりノロウィルスによる嘔吐・下痢症が流行ります。
症状は、感染後24〜48時間の潜伏期間をおいて吐き気、嘔吐、下痢、腹痛が起こります。
発熱は軽度です。通常は1〜2日症状が続いた後に、自然に治癒します。
治療法は、残念ながら特効薬はありません。
嘔吐・下痢のため脱水となりますので、電解質を含む十分な水分摂取が必要です。
経口摂取が困難な場合は、点滴にて脱水を改善します。
薬物療法としては、吐き気止めや整腸剤が使われます。
ノロウィルスは感染力が強く、感染しても免疫を獲得しにくため同じシーズンでも何度でも感染することがあります。
ノロウィルスは、10〜100個程度のわすかなウィルス量で感染する力を持っています。
感染者の嘔吐物1gの中に100万個以上、糞便1gの中に1億個以上のウィルスがいますので、これらを介して大規模な集団感染を起こすことがあります。
従って、糞便や嘔吐の処理には慎重な対処が必要です。
糞便や嘔吐物が乾燥するとウィルスが空気中に拡散し感染の拡大を起こしますので、先ずは速やかな処理が必要です。
消毒には、塩素系消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムが有効で、濃度が200ppmで5分間、1000ppmで1分間でウィルスを死滅するとされています。
処理法は以下のとおりです。
1)使い捨ての手袋とマスクを使用し、使用後は必ず廃棄します。
2)糞便や嘔吐物の上にペーパータオル等で覆いウィルスの拡散を防ぎます。覆ったタオルを1000ppm濃度の次亜塩素酸ナトリウムで浸し、5〜10分放置します。
3)その後、タオルで拭き取ります。外側から内側に拭き取り汚染面積を拡げないようにします。
4)拭き取った後の部分は、200ppm濃度の次亜塩素酸ナトリウムで浸すようにさらに拭き取り、最後に水ぶきをします。
カーペットなどの色落ちが困るものは、95度で1分間のアイロンがけをします。
5)処理に使用したものは、すべてビニール袋に入れてその中にも1000ppm濃度の次亜塩素酸ナトリウムを入れます。
6)その後、十分な石鹸水で時間をかけて手洗いをします。
7)最後に部屋の空気を外に出すように換気をします。
感染経路としては、経口感染、接触感染、飛沫感染、空気感染があります。
飛沫感染や空気感染予防のためには、上記の糞便・嘔吐物の処理に注意を要します。
経口感染、接触感染予防には、手指の消毒や汚染物の消毒が必要です。
ノロウィルスは、85度以上で1分以上の加熱で死滅するとされています。
二枚貝などの食品は、中心部まで1分以上しっかり加熱することが必要です。
また、下痢・嘔吐の症状が治った後も1週〜1ヶ月間ウィルスを排泄していることがありますので、 症状消失後も十分な手洗いなどの注意が必要です。
次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方は、原液を希釈します。
原液には、約5%のものと約10%のものがあります。
市販されている家庭用塩素系漂白剤(ハイター、ブリーチなど)は約5%です。
5%原液による消毒液の作り方は、
1)糞便や嘔吐物による汚れがひどい場合:100ml
2)糞便や嘔吐物が付着の場合:20ml
3)衣類や器具の浸けおき:10ml
4)トイレの便座、ドアノブ、手すり、床など:4ml
を約1,000ml(1リットル)の水に入れればよいです。
消毒液の注意事項は、以下のとおりです。
1)消毒液作成時には、塩素ガスが発生しますので換気に気をつけてください。
2)皮膚や粘膜への刺激が強いため、手洗いには使わないでください。消毒液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水洗いしてください。
3)金属に対しては腐食性があるため、金属の消毒後は水洗いするか拭き取るようにしてください。
4)漂泊作用のため色が変色することがありますので、床などの変色に気をつけてください。
5)効果が薄れるので、作り置きをしないでください。
塩素は日光により分解しますので、原液は直射日光や高温を避けて保存してください。
Q2.膀胱炎について
A.
膀胱炎は小児から老齢者までよく見られ、泌尿器科・内科・小児科・婦人科など様々な科を受診されることが多い病気です。
特に女性では,、尿道口(尿の出口)から膀胱までの距離が短かく、細菌が膀胱に入りやすい解剖学的特徴があるため多く発症します。
急性膀胱炎の三大症状として、 1)排尿痛 2)頻尿 3)混濁尿が挙げられます。
その他の症状としては、残尿感、血尿、下腹部不快感、下腹部痛、尿漏れなどがあります。
尿検査により尿中の白血球、赤血球、細菌を確認することで、診断ができます。
適切な抗菌剤(抗生物質や合成抗菌剤)の服用で比較的簡単に治癒しますが、近年では薬剤耐性菌による膀胱炎のため治療が困難なこともあります。
また、十分な水分摂取で利尿をつけることにより膀胱内に繁殖の細菌を洗い流す効果があり、炎症の進行を止める効果もあります。トイレを我慢すると膀胱内に侵入した細菌が繁殖しやすくなりますので、排尿を我慢しないことも大切です。
Q3.過活動膀胱について
A.
トイレが近い症状がある場合、Q2.で述べたように膀胱炎が原因のこともありますが、過活動膀胱という病気の場合があります。
過活動膀胱とは、文字通り膀胱の働きが活動し過ぎる状態をいいます。
即ち、膀胱内にあまり尿が溜まっていないにも関わらず膀胱の機能が活動しすぎて急に尿意を催し頻尿になる状態です。
日本排尿機能医学会の過活動膀胱診療ガイドラインで、診断のために以下の表が示されています。
| 質問 | 症状 | 点数 | 頻度 |
| 1 | 朝起きた時から寝るときまでに、何回くらい尿をしましたか | 0 | 7回以下 |
| 1 | 8~14回 | ||
| 2 | 15回以上 | ||
| 2 | 夜寝てから朝起きるまでに、何回くらい尿をするために起きましたか | 0 | 0回 |
| 1 | 1回 | ||
| 2 | 2回 | ||
| 3 | 3回 | ||
| 3 | 急に尿がしたくなり、我慢が難しいことがありましたが | 0 | なし |
| 1 | 週に1回より少ない | ||
| 2 | 週に1回以上 | ||
| 3 | 1日1回くらい | ||
| 4 | 1日2〜4回 | ||
| 5 | 1日5回以上 | ||
| 4 | 急に尿がしたくなり、我慢できずに尿をもらすことがありましたか | 0 | なし |
| 1 | 週に1回より少ない | ||
| 2 | 週に1回以上 | ||
| 3 | 1日1回くらい | ||
| 4 | 1日2〜4回 | ||
| 5 | 1日5回以上 | ||
| 合計点数 | 点 | ||
合計点数が5点以下は軽症、6〜11点は中等症、12点以上は重症と考えれます。
日常生活の注意点としては、水分摂取量を少し減らす、排尿の回数を減らし尿意を少し我慢する、骨盤底筋の体操をするなどがあります。
薬物療法としては、抗コリン剤により排尿筋を調節する神経を調整し膀胱の過剰な収縮を抑制する方法があります。
Q4.便秘について
A.
慢性便秘症診療ガイドライン2017では、
便秘は「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態。」
と定義されています。
便秘症は、便秘による症状が現れ、検査や治療が状態を言います。
症状としては、
1)排便回数の減少によるもの(腹痛、腹部膨満感など)
2)硬便によるもの(排便困難、過度の怒責など)
3)便排出障害によるもの(軟便でも排便困難、過度の怒責、残便感とそのための頻回便など)
があります。
慢性便秘症の診断基準は、
1.「便秘症」の診断基準
以下の6項目のうち、2項目以上を満たす
a.排便の4分の1超の頻度で、強くいきむ必要がある。
b.排便の4分の1超の頻度で、兎糞状態または硬便である。
c.排便の4分の1超の頻度で、残便感を感じる。
d.排便の4分の1超の頻度で、直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある。
e.排便の4分の1超の頻度で、用手的な排便介助が必要である。(摘便・会陰部圧迫など)。
f.自発的な排便回数が、週に3回未満である。
2.「慢性」の診断基準
6か月以上前から症状があり、最近3か月間は上記の基準を満たしていること。
となっています。
問診票により症状、病歴、服薬、排便様式および排便に関する環境、警告症状や危険因子などを網羅して質問し、診断しています。
質問票
治療は、内服薬など保存的治療が基本となります。
慢性便秘症の治療として、上皮機能変容薬が推奨されています。ルビプロストン(商品名アミティーザ)やリナクロチド(商品名リンゼス)があります。
また、浸透圧性下剤も推奨されています。代表的薬剤として酸化マグネシウム(商品名マグミットなど)があります。
便秘症に用いられる主な治療薬(慢性便秘症診療ガイドライン2017)
| 分類 | 代表的薬剤 | 作用機序 | ガイドラインのステートメント | 推奨の強さ | エビデンスレベル |
| プロバイオティクス | ビオフェルミンなど | 腸内細菌のバランスを整える | 慢性便秘患者において排便回数の増加に有効であり、治療法として 用いることを提案 |
2 | B |
| 膨張性下剤 | バルコーゼ、 コロネル |
便を膨潤・ゲル化し排便を促す | 便秘型過敏性腸症候群に使用することを提案 | 2 | C |
| 浸透圧性下剤 | マグミット、 マグコロール、 ラグノスNF |
腸内の浸透圧を高めて腸壁から水分を引き寄せ軟便化し排便を促す | 慢性便秘症に対して有用であり、使用することを推奨。ただし、マグネシウムを含む塩類下剤使用時は、定期的なマグネシウム測定を推奨 | 1 | A |
| モビコール | 腸管内の水分量 を増加させ水分を保持し、軟便化や便容積増大により排便を促す | (ガイドライン未掲載) | |||
| 刺激性下剤 | プルゼニド、 ラキソベロン |
大腸を刺激し蠕動運動を促進する(ラキソベロンは腸管の水分吸収を抑制し軟便化する作用も持つ) | 慢性便秘症に対して有効であり、頓用または短時間の投与を提案 | 2 | B |
| 上皮機能変容薬 | アミティーザ、 リンゼス |
腸液の分泌を促進し軟便化し排便を促す(リンゼスには痛覚過敏抑制作用による腹痛改善効果もある) | 慢性便秘症に対して有用であり、使用することを推奨。ただし、アミティーザは妊婦には投与禁忌であり、若年女性に生じやすい悪心の副作用にも十分に注意する必要がある | 1 | A |
| 胆汁酸トランスポーター阻害薬 | グーフィス | 胆汁酸の再吸収を阻害して大腸の蠕動運動と水分泌を促進、排便を促す | (ガイドライン未掲載) | ||
A.
厚生労働省健康局結核感染症課より、抗微生物薬適正使用の手引きが発刊されています。
国立国際医療研究センター病院AMR臨床リファレンスセンターから、その内容に準じたリーフレットが出されています。
急性気道感染症は、急性上気道感染症(急性上気道炎)および急性下気道感染症(急性気管支炎)を含み、一般的には「風邪」、「風邪症候群」、「感冒」などと言われています。
急性気道感染症においては、抗菌薬が必要なものと不必要なものを見極める必要があります。
いわゆる「風邪」として受診される病態には、感冒、急性鼻副鼻腔炎、急性咽頭炎、急性気管支炎が含まれます。
| 病型 | 鼻汁・鼻閉 | 咽頭痛 | 咳・痰 |
| 感冒 | △ | △ | △ |
| 急性鼻副鼻腔炎 | ◎ | × | × |
| 急性咽頭炎 | × | ◎ | × |
| 急性気管支炎 | × | × | ◎ |
治療方法としては、
1)感冒
感冒に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
2)急性鼻副鼻腔炎
成人では、軽症の急性鼻副鼻腔炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
成人では、中等症又は重症の急性鼻副鼻腔炎に対してのみ、以下の抗菌薬投与を検討することを推奨する。
(成人における基本)
アモキシシリン水和物内服5〜7日間
学童期以降の小児では、急性鼻副鼻腔炎に対しては、遷延性又は重症の場合を除き、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
学童期以降の小児の急性鼻副鼻腔炎に対して、遷延性又は重症の場合には、抗菌薬投与を検討することを推奨する。
(小児における基本)
アモキシシリン水和物内服7〜10日間
3)急性咽頭炎
迅速抗原検査又は培養検査でA群β溶血性連鎖球菌(GAS)が検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎にたいして抗菌薬投与する場合には、以下の抗菌薬投与を検討することを推奨する。
(成人・小児における基本)
アモキシシリン水和物内服10日間
4)急性気管支炎
慢性呼吸器疾患等の基礎疾患や合併症のない成人の急性気管支炎(百日咳を除く)に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
基本は、
1)ウイルス感染には抗菌薬が効果がない。
2)咳は4週間ぐらい続くことがある。
3)大部分は自然軽快する。
4)身体が病原体にたいして戦うが、良くなるまでには時間がかかる。
5)十分な栄養、水分をとり、ゆっくりと休む。
で、むやみに抗菌薬が使用しないことが原則です。
鈴峰今中医院医療法人社団 鈴峰今中医院
〒733-0842
広島市西区井口4-2-31
TEL 082-277-1223
FAX 082-277-1538